Interviewインタビュー 日中21世紀交流事業に参加された方々に交流を振り返っていただきました
Vol.77 大学生交流事業への参加経験者3人による座談会-前編-
「あの時の挑戦が今の自分を作った」

大学生交流事業に参加した経験を持つ3人が集まり、異なる立場から当時の体験を振り返りつつ、交流事業で得られたものや今に役立っていることについて語り合います。
プロフィール
南 有紗さん
2017年に大学生交流事業へ参加。杭州ふれあいの場で現地の学生たちとともにイベントを実施。現在、社会人6年目。組織の人材開発や組織開発を支援する営業職として活躍中。
仁平信孝さん
2021年に大学生交流事業へ参加。オンラインで長沙ふれあいの場と交流。その後、2023年にふれあいの場サポーター活動に参加(ハルビンふれあいの場と交流)。同年、中国ふれあいの場学生代表訪日研修に、学生コーディネーターとして参加。2023年~1年間、ハルビンにある黒龍江大学へ留学。現在大学4年生。
陳妍宇さん
元成都ふれあいの場の学生。2017年に日本の学生たちを迎え、大学生交流事業を実施。現在は日本の証券会社の投資銀行部門にて勤務。

大学生交流事業で印象に残ったこと
――大学生交流事業に参加した理由を教えてください。
南:大学2年生の時、同じ大学の友人から誘われたのがきっかけです。その友人は大学の特別授業でネパールに行ったときのルームメイトでした。中国に特別な関心があったわけではないのですが、公費プログラムで海外に行けることに魅力を感じて、参加を決めました。
仁平:僕が大学生交流事業に参加したのは、大学1年生の冬から春にかけてのことです。大学の第二外国語で選んだ中国語のクラスメイトに誘われたのがきっかけでした。中国語を学べる機会になるし、大学生になったら何かチャレンジしたいと思っていたこともあり、参加を決めました。残念ながらコロナ禍で渡航はできず、日本と中国とを結んでのオンラインイベントにはなりましたが、楽しい交流ができました。
――大学にも通えない時期にオンラインイベントを開催したのですね。
仁平:大学で友だちができるより先に、中国の学生の友だちがたくさんできました(笑)
――陳さんは、日本の学生を迎える側として参加されたのですね。
陳:はい。私は中国の大学で日本語を専攻していたので、日本語上達のために成都ふれあいの場に通っていました。そこでは大学の先輩がボランティアをしていたので、私も自然に活動に加わっていきました。ふれあいの場には日本に関する多彩なプログラムがあり、その一つに学生交流事業があって「日本の学生が来る!」と聞いて自然に参加しました。
――南さんと陳さんは現地でお客さんを招いての対面イベントを開催していますが、特に印象に残っていることはありますか?
南:現地に着いて5日目には本番というスケジュールだったので、準備に追われました。事前にオンラインで打ち合わせはしていたものの、やはり情報の行き違いも多々あり、ふれあいの場の学生が私たちのホテルに来てくれて、一緒に準備作業を進めたことが印象に残っています。そうしたタイトなスケジュールの中、無事成功させることができたときは、それまでの苦労が報われた気がして、充実感がありました。
陳:私も深夜12時、1時まで準備や打ち合わせをしていたことが記憶に焼き付いています。しかも、直前になって予定になかった舞台劇をすることになり、メンバー全員が騒然となりました。台本は私があらかじめ用意していたのですが、日本語が話せない中国人、中国語が話せない日本人の学生も多かったのでドキドキでした。でも、みんな一生懸命セリフを覚えて演じてくれて、お客さんからも大好評だったので達成感がありました。
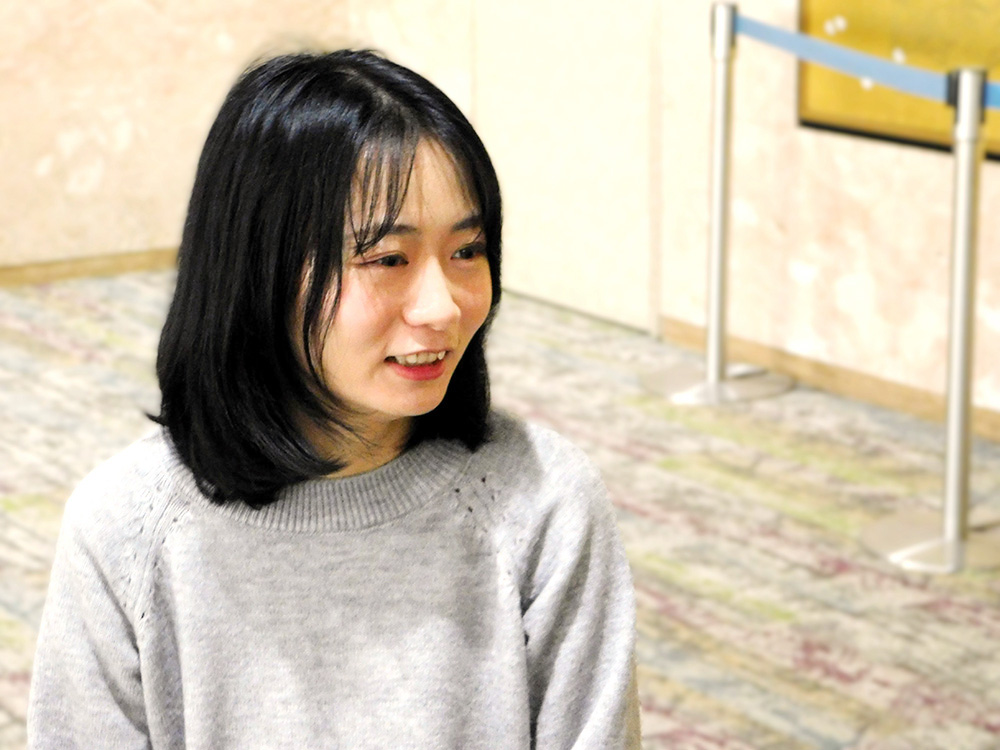
――仁平さんはその後、国際交流基金の他の事業にも参加されていますが、これまでで特に印象に残っていることはありますか?
仁平:2023年の「中国ふれあいの場学生代表訪日研修」に学生コーディネーターとして参加した時のことが特に印象に残っています。日本に来たふれあいの場の学生たちに、日本の名所を案内する役割を務めたのですが、私にとっては初めて中国の学生と同じ場所でともに行動をする機会でした。やはり対面だと人と人が自然に仲良くなることができ、オンライン交流との違いを感じました。
交流イベントの経験がもたらしたもの
――大学生交流事業への参加は、みなさんにどのような影響をもたらしたでしょうか?
南:私は社会人になって6年が過ぎ、現在は組織の人材開発や組織開発を提供するサービスの営業に携わっているのですが、人と組織がどう動くかといったことに関心を持つきっかけになりました。1週間という限られた期間に大人数を動かして1つのプロジェクトを成し遂げるというのは、つまりプロジェクトマネジメントですよね。
私は今、多様な人たちがそれぞれの強みを生かして活躍してほしいとの思いで人事領域の仕事に携わっていますが、その思いを強くしたきっかけの1つにあのイベントがあります。大学に入学した時は学校の教員になりたいと思っていたのですが、多様な人が輝く社会を支える方法やフィールドは他にもたくさんあるという視点を持つきっかけにもなりました。

陳:私は今、日本の証券会社で金融関連の仕事をしていますが、日本語専攻だった自分がまさか金融業界で働くことになるとは想像もしていませんでした。それも学生時代に成都ふれあいの場での活動を経て日本に交換留学に来て、そこで日本企業をいくつも訪問したことが日本の大学院で経営学を学ぶきっかけになり、今の私があります。
日本で仕事をしようと思えたのも、あの時日本の学生と一緒にイベントを作った経験があったからです。他にもいくつかの日中交流イベントに携わる機会があり、やればできるという自信がついたことも、海外で働くうえでの心の支えになっています。
――仁平さん、社会人として活躍する二人のお話は何か参考になったでしょうか。
仁平:素直にすごいなと思いました。僕は1年間中国留学をしていたので、来年の春に大学を卒業する予定ですが、まだその先のことは決めていません。日中交流や留学の経験がどのように将来に繋がるかわかりませんが、自分のペースで働ける場所を見つけたいと思っています。
(後編につづく)
取材・文:大島 七々三 取材日:2025年2月11日
![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)











![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)