 写真を拡大社会人1年目の潘さん。多忙な毎日だが、会社ではバトミントンのサークルに入り、休日にはジョギングをしたり、友人と食事に行ったりするなどして、社会人生活を楽しんでいる。
写真を拡大社会人1年目の潘さん。多忙な毎日だが、会社ではバトミントンのサークルに入り、休日にはジョギングをしたり、友人と食事に行ったりするなどして、社会人生活を楽しんでいる。
名前
潘 撼(ぱん はん) さん
プロフィール
1989年生まれ。遼寧省瀋陽市出身。東北育才学校の高校2年のとき、「心連心・中国高校生長期招へい事業」第一期生として、2006年9月から約1年間、茨城県の土浦日本大学高等学校に留学。
帰国後、東北育才学校を卒業したのち、東京大学理科一類に進学し再び日本へ。さらに同校の修士課程まで進み、2015年4月、ソニー株式会社に就職した。
テレビカメラの向こうの留学生
日本の高校生たちがおそろいのエプロンをつけ、餃子を包む様子を、テレビカメラが追っている。家庭科の授業だろう。カメラが一人の中国人留学生をアップで映し出すと、インタビューアーが、「餃子の包み方は中国式か日本式か」などと聞く。
留学生は「どちらも一緒ですよ」「先生が包むほうが、母親が包むよりも上手かも」などと淡々と答える。聡明さと芯の強さを感じさせる落ち着いた表情の中に、どこかあどけなさも残る。
続いてカメラは隣の男子生徒を映し、この留学生についての印象をたずねた。男子生徒は、「的確に発言していて、発言力があってすごいと思う」と答える。また、別の女子生徒は「すごく頭がよいけれど、すごくやさしい」などとコメントする。
これは2007年4月に温家宝前首相が来日した際、中国で放映された中国中央テレビの「白岩松看日本(白岩松が見た日本)」というドキュメンタリーシリーズの1シーンだ。
登場した中国人留学生は、潘撼さんという。当時、「心連心・中国高校生長期招へい事業」第1期生として、茨城県の土浦日本大学高等学校に留学し、約7カ月がたとうとしていた時だ。
大人っぽい少年から思慮深い青年へ
あれから約8年。潘さんは今、日本で社会人1年生をしている。テレビでは少し大人っぽい少年という感じだったが、今ではすっかり思慮深そうな青年に変わっていた。
この8年間、潘さんの歩いてきた道のりは、いわゆる「エリートコース」だったと言えるだろう。心連心での留学を終えたあと、中国の高校を卒業し、東京大学理科一類に進学した。大学院はそのまま同校の修士課程に進み、修了後はソニー株式会社に就職、現在は同社の開発部署で働いている。
朝9時に出勤し、会社の寮に戻るのは夜8~9時という多忙な毎日で、「海外では、こんなに働く人たちはめったにいない気がする」と苦笑する。
流暢な日本語を話す姿は、もう日本人と変わらない。すっかり日本社会に溶け込んでいるように見える潘さんだが、ここにいたるまでには、小さな努力の積み重ねもあった。
辛かったことは寂しかったこと
潘さんと日本の関わりはずいぶん長い。最初に興味を持つようになったのは、小学生のころだった。父親の影響で囲碁を始めたのがきっかけだ。囲碁は世界でも日中韓が強い。そこで日本に関心を持つようになり、中学の時、日本語クラスを選択した。
高校でも日本語クラスに進み、いつか日本に行きたいと思っていた。だから、留学のチャンスが巡ってくると、さっそく申し込んだ。
両親も「ぜひ行ったらいい」と背中を押した。潘さんの両親は「私が自分でいろいろ考えてやっていることには口出ししない」というタイプで、いつも一人息子の自立を促し、支えてくれているそうだ。
こうして初めて訪れた異国での生活は、「刺激が大きかった」と、潘さんは振り返る。事前に日本語能力試験1級を取得していたが、日常会話のハードルは少々高かった。最初は授業もあまり聞きとれなかったと言う。
しかし優秀な潘さんのこと。ほどなくして言葉の問題はなくなった。むしろ、カルチャーショックのほうが大きかった。
「高校1年までずっと中国にいて、それまではただひたすら勉強すればよかったのですが、日本ではいかに周りに溶け込んでゆくかなど、いろいろ考えることがありました」
留学先では寮暮らしで、学生同士の交流はあまりなかった。加えて日本人特有の微妙な距離感がなじめなかった。特に彼の出身地である東北地方は、中国の中でも人と人の関係が直接的で密だ。日本人の親切だが一歩引いたような付き合いに難しさに感じた。
「嫌なことはなかったですが、寂しいことが辛かった」と潘さん。それでも体育祭や、バトミントン部などを通じて、徐々に打ち解けていった。
ホストファミリーから受けた無償の愛
 写真を拡大高校時代、3ヶ月ほど御世話になったホストファミリーの「父」と潘さん。大学進学後も、連休などを利用して、会いに行っているそうだ。
写真を拡大高校時代、3ヶ月ほど御世話になったホストファミリーの「父」と潘さん。大学進学後も、連休などを利用して、会いに行っているそうだ。
中でも思い出深かったのは、留学生活の残り約3カ月で体験したホームステイだ。学校の先生の関係で、ホストファミリーを申し出てくれる人がいて、寮を出た。それまでにもクラスメイトの家などにショートステイをしたことはあったが、ここで改めて、「日本人の生活」を体験することになった。
「すごくよくしてもらいました」と、潘さん。
「ホストファミリーには謝礼金が出るそうなのですが、最初、受入当初はそれも知らなくて、本当にお金に関係なく、親切に接してくださいました」
一度、両国まで相撲を見に連れていってもらった時には、「留学生のために朝青龍や白鵬のサインをもらえないか」と、事前に問い合わせをしてくれたと言う。残念ながら、もらうことはできなかったが、「非常に感動しました」と話す潘さんの顔は明るい。
こんな体験を通じ、「日本が大好きになった」と言う潘さんは、大学でも引き続き日本に留学することを決心した。
国際交流のサークルで
 写真を拡大大学1年のとき、東大伝統の五月祭で、クラスメイトたちとチョコバナナの屋台を出店したことも楽しい思い出の一幕だ。
写真を拡大大学1年のとき、東大伝統の五月祭で、クラスメイトたちとチョコバナナの屋台を出店したことも楽しい思い出の一幕だ。
東京大学に進学後、1、2年の時に所属したサークルは、もう1つの「転機」だったと言えるかもしれない。それは「LEAF」という国際交流サークルだ。「LEAF」は当時、主に日本の東京大学、中国の北京大学が中心となり、さらに韓国のソウル大学も加わって、年に1回、学生フォーラムを開催していた。
開催地は年ごとに東京や北京など変わった。議題も経済や歴史問題などさまざまで、教科書問題を話し合ったこともある。日中関係は「最悪の時期」だったが、逆にそれが学生たちの真摯な交流にもつながった。
また、サークル運営を通じて、各国トップ校の学生たちと知り合うことで、それぞれの国のよさに目を向けることもできた。
 写真を拡大大学1、2年のときに所属したサークル「LEAF」で開催した観光フォーラムの1シーン。東京の外国人向け観光インフラを調査するため、北京大の学生たちと、国技館のある両国に繰り出した。
写真を拡大大学1、2年のときに所属したサークル「LEAF」で開催した観光フォーラムの1シーン。東京の外国人向け観光インフラを調査するため、北京大の学生たちと、国技館のある両国に繰り出した。
「サークルを運営していると、日本と中国では準備の仕方が違います。日本側は半年間かけてコツコツと準備をしますが、中国側は2週間で準備します。おおざっぱですけれど、スピード感はすごいです」
潘さんはそんな例をあげる。それは人との付き合い方の違いにも通じる。
「日本人は自分のことばかり考えたりせず、思いやりと気遣いがあって、そういうところがいいなと思います。そのために、向上心が薄れて競争しなくなるのはよくないですが、普段の生活の中で、人にも気を配れるというのはいいところだと感じます」
逆に中国人は個人主義的なところがある一方で、外国人にも壁を作らず自然に接するところがあると、潘さんは感じている。また国際意識も違う。
「北京大学ではほとんどの学生が、学部の4年間のうちに、少なくとも半年間くらいは留学をしています。でも日本ではそこまで留学する人は多くありません」と、潘さんは語る。
「中間人間」でありたい
両国を冷静に見据える潘さんからは、これまでの留学生活の中で、日本と中国のよいところをほどよく融合させてきたような印象を受ける。
「日本に留学した人の中には、日本が大好きで、中国には帰りたくないという人もいます。でも、私は『中間人間』のままでいいかなあと思っています」と、潘さん。
潘さんにはこのサークル時代に知り合った中国人の親しい友人がいる。当時、北京大の学生だった友人はアメリカに留学し、今は北京で就職している。
「この友人は、日本語は話せませんが、日本も好きで、国際的な人です。その影響もあるかもしれません。」
「こうした友人を通じて、中国の優秀な人たちと接することで、日本にいるだけでは見えなかった世界も知ることができた。今後は、さらにグローバルな世界で、技術面でのコンサルティング的な仕事をしたいと考えている。」
「まずは、自分の専門性をかためて、将来的にはビジネスと技術を結びつけるような仕事をしてゆきたいです。」
そう語る潘さんは、日本人的な細やかさと中国人的なダイナミックさをあわせもち、いつか世界を舞台に「アジア人」として、羽ばたいてゆくことだろう。
 写真を拡大社会人になって2ヶ月、季節のよい6月に、同期2人と鎌倉に出かけた。
写真を拡大社会人になって2ヶ月、季節のよい6月に、同期2人と鎌倉に出かけた。
【取材を終えて】
潘さんは常に淡々と、慎重に、言葉を選ぶように話す。日中の違いについて語りながら、どちらの国の価値観も決して否定しない。まだ二十代半ばなのに、成熟した大人と話しているような印象を受ける。けれど、ときおり茶目っ気ものぞく。「同僚2人と鎌倉に行った」という潘さんの話に、思わず「鎌倉に男3人!」と言葉を返すと、「女子力、上げました」などと冗談めかした。中国と日本が上手くミックスしたような潘さんに、「中国+日本」発の国際人としての活躍を期待したい。
(取材・文:田中奈美 取材日:2015年11月22日)
![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

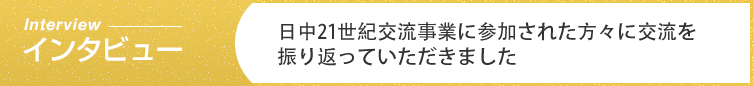












![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)