 写真を拡大東京大学の赤門前にて。
写真を拡大東京大学の赤門前にて。
名前
黄 哲(こう てつ) さん
プロフィール
1993年生まれ、瀋陽市出身。東北育才外国語学校で日本語を学ぶ。2009年9月〜2010年7月、「心連心」第4期生として、群馬県立前橋高等学校に通う。帰国後、東北育才外国語学校を卒業したのち、2013年4月より東京大学法学部政治学科に入学。
小学生のときから新聞を愛読
 写真を拡大前橋高校で、中国の高校を紹介する黄さん。高校時代は唯一の留学生ということもあり、知らない学生からも「あ、黄くん!」と声をかけられることもあったそう。
写真を拡大前橋高校で、中国の高校を紹介する黄さん。高校時代は唯一の留学生ということもあり、知らない学生からも「あ、黄くん!」と声をかけられることもあったそう。
東京大学で政治学を学ぶ黄哲さんは、小学生のころから、「環球時報」を愛読していたという。「環球時報」は中国共産党機関紙「人民日報」系の保守色が強い硬派な新聞だ。
父親から新聞代をもらい、小学校に行く途中、自転車でやってくる新聞売りから「環球時報」を買って、学校で読んでいた。
そんな話を聞くと、いかにも早熟で堅物そうなイメージだが、実際の黄さんは、内気ではにかみやの青年という印象だ。小さな声で訥々と話し、ときどき、にこりとやさしい笑顔になる。
新聞を読むようになったきっかけを聞くと、「さあ、どうでしたでしょうか」と首をひねった。父親は旅行好きのサラリーマン、母親は図書館勤務。小さいときから、本もたくさん読んでいたが、特に両親の影響があったというわけでもない。
ただ、いつのまにか、政治や国際紛争などに興味は持つようになっていた。
「小学校高学年のころ、イラク戦争が起き、号外を買って読んだり、テレビのスペシャル番組を見たりしました。覚えているかぎりでは、特にそのころから、興味を持ち始めたと思います」
そんな黄さんが日本留学を意識するようになったのは、中学生のときのことだ。黄さんが進学した東北育才外国語学校は、瀋陽の東北育才学校と、京都の関西語言学院の合弁学校で、中学三年になるとほとんどの学生が、第二外国語で日本語を選択すると言う。
高校卒業後、日本の大学に進学する学生も多く、学校のパンフレットの進学実績には、東京大学や京都大学など日本の有名大学の名前が並んでいた。それに憧れを抱いた黄さんは、自分も日本に留学したいと考えるようになったそうだ。
また、小学校生のときに見たアニメ「デジモンアドベンチャー」の影響で、もともと日本に関心もあった。
大学留学の前に、もっと日本を知りたい――。そんな思いから、黄さんは心連心の高校留学への参加を決めた。
心連心の留学先で有名人に
 写真を拡大心連心の留学でお世話になったホストファミリー宅でケーキづくりを手伝う。「たぶんクリスマスのときだったと思う」と黄さん。
写真を拡大心連心の留学でお世話になったホストファミリー宅でケーキづくりを手伝う。「たぶんクリスマスのときだったと思う」と黄さん。
日本は初めてだったが、外国生活はそれまでも経験があった。小学校低学年のとき、父親の仕事の関係で、半年ほどアメリカで過ごした。中学三年生のときは、シンガポールの学校との交換留学に、一週間ほど参加したこともある。
ただ、約1年間という長期で、親元を離れるのはこれが初体験だった。
留学先では高校二年生に編入した。中国にはない「男子校」というのが、新鮮だった。
「思春期に異性の目を気にしなくていい」のが楽だったが、「最初はなかなか友達ができませんでした」と、黄さん。
日本語は、中国でも勉強していたものの、話し言葉となると、やはり難しい。ある時、日本のニュースを読もうと、駅の売店に新聞を買いに行ったら、言葉がうまく通じず、年配女性の店員に戸惑われたこともあった。
入部したギターマンドリン部では、マンドリンが何か知らず、「マンドリンのマンは英語の『man(男性)』だと思っていました」と笑う。
でもその部活で、コンテスト前に、夜遅くまで「ガチな練習」に励んだことはよい思い出となっている。
残念ながら、入賞はできなかったが、このとき、練習をともにした同級生と、つい先日、数年ぶりに再会を果たした。フェイスブックで黄さんのアカウントを見つけ、連絡してくれたそうだ。
三年生にあがると、ようやく友達もできるようになった。同じ高校の知らない学生から、声をかけられることもあったという。
唯一の留学生だったこともあり、どうやら、学校ですっかり有名人になっていたらしい。黄さんに自覚はなかったようだが、のちに、「生徒会長に次ぐ有名人だった」という話を聞いたそうだ。
当時、黄さんを担当していた日中交流センターの職員は、「高校入学当初から、日本語力が高く、テストの成績もよくて、非常に優秀でした。本人もとても努力していました」と語る。
「いつもニコニコしていて、素直な子です。私と話す時は、自分が優秀だということをアピールしたり、自慢したりもしません。そういうところも、皆さんに好かれる理由なのではないかと思います」
先生たちからの評判も非常によく、当時の教頭先生は「日本人の生徒には見習って欲しい」と話していたそうだ。日本人高校生にもよい刺激になっていたようで、そんなところも、有名人となった理由の一つかもしれない。
違う立場で物事を見る
 写真を拡大東大で日・中・韓の大学生の交流サークルに入り、北京フォーラムに参加。日本、中国、韓国の大学生たちが集まった。
写真を拡大東大で日・中・韓の大学生の交流サークルに入り、北京フォーラムに参加。日本、中国、韓国の大学生たちが集まった。
しかし心連心の留学時代を振り返ると、反省することがあると、黄さんは言う。
一つは、一人っ子として育ち、親に、身のまわりのことを何でもしてもらっていて、それを当たり前だと思っていたことだ。
ホストファミリーのお母さんに、食事を出してもらっても、「おいしかった」と言うことも思いつかず、ずいぶん寂しがられた。
このとき、「他人の気持ちを考える」ことを学んだ。
もう一つ、後悔しているのは、学校で日中関係について話をしたとき、「自己主張」しすぎたことだ。靖国問題などについて、「自説」を披露したが、それは愛読していた中国の新聞や、テレビメディアなどの受け売りで、自分の考えではなかったことに、あとで気づいた。
留学先の高校の図書館で、『日本の論点』を読み、一つのテーマで賛成と反対の意見が書かれているのを見て、違う立場で物事を考えることを学んだ。
「いろいろな立場の見方を知れば知るほど、かつての考えは偏っていたと思うようになりました。だから日本の大学に進んだあとも、たくさんの本を読み、さまざまな情報を知りたいと思いました」
黄さんはそんな風に話す。
中国に戻ったあと、本来なら高校三年生になるところだったが、一年「留年」する形で、高校二年生に編入した。後輩だった学生たちが同級生になり、戸惑いもあった。
でも、「両方の学年に友達ができてよかった」という言葉に、人柄がにじむ。
東京大学法学部に進学
 写真を拡大東大法学部にて。
写真を拡大東大法学部にて。
そして、2013年、東京大学法学部政治学科に進学した。また友達づくりに苦労するのではないかと心配したが、幸い、同じ東北育才外国語学校出身の留学生も多い。前橋高校からも何人か東大に進んでいた。
しかし、そのシャイな性格から、事前に大学の様子をたずねにくく、所属する学部では「最初の二年間は教養学部に行く」ということを知らなかった。
「入学初日、駒場東大駅前を降りたら、門のところに教養学部と書いてあるのを見て、法学部ではなかったのかとびっくりしました」というエピソードが、黄さんらしい。
大学では、とにかく、勉強に追われた。2年生までは、日・中・韓の交流サークルに入ったり、友達と何時間もおしゃべりをしたりする時間もあったが、3年にあがると、学校と家を往復するだけの毎日になった。
勉強以外にすることといえば、もっぱら校内のジムに行くか、ネットニュースを見るくらいだった。
特に、期末試験が大変だったそうだ。論述の試験が多く、問題を開いた瞬間に解答していかないと間に合わないほどの分量で、時々、山をはずして「しまった」と思うこともあったと語る。
クラスメートには、国家公務員や弁護士を目指し、家で試験勉強している学生も多かった。「東大法学部は『砂漠の学部』といわれるのですが、本当に、孤独死するかと思いました」と笑う。
友達に食事に誘われても、必要以上の「遊び」は控え、とにかく勉強に励んだ。
幸せな瞬間はカラオケ
そうした中で、思い出に残ったのは、台湾大学との交流プログラムに参加し、2週間ほど台湾に滞在したことだ。
現地の学生たちとの交流を通して、台湾の現実を知った。
「馬英九政権時代でしたが、総統府でスポークスマンにもお会いしました。若くてイケメンで、イギリス留学経験があり、英語もすごく堪能でした。台湾大学の学生の厳しい質問にもうまく対応していて、印象深かったです」
実はこのとき、現総統の蔡英文氏にも面会する機会があった。当時からすでに将来、総統になるだろうと言われていたそうで、貴重な体験となった。
ストイックで真面目で、がり勉。
そんな印象の黄さんに、「一番、幸せを感じる瞬間は?」とたずねると、長い沈黙のあとに、「カラオケかな」とぽつり。
なんとも意外な回答が返ってきた。
友達と一緒に行くこともあるが、「ヒトカラ」すなわち一人カラオケに行くこともあると言う。
短いときは30分くらい、長くても1時間程度。ただ、大学院入試のあとは、試験のおわった日の夜12時から朝4時頃まで、一人で歌いまくったそうだ。
「歌っているときはありのままの自分でいられる」と、黄さんは話す。
今、目指しているのは、研究者の道だ。海外にいる立場から、中国の政治を研究したいと考えている。
小学生のとき、新聞で世界を見ていた少年は、リアルな体験を一つ一つ積み、幼いころの興味を現実のものに変えようとしている。
そのぶれない姿勢が、やがて大きな成果につながってゆくことに、エールを送りたい。
【取材を終えて】
取材の間中、遠慮がちに話をしていた黄さん。日本で「人の気持ちを大事にすることを学びました」と繰り返し話していたのが印象的だった。
でもその調子で、中国で遠慮をしていると、「遠慮しすぎ!」と相手に嫌がられることもある。だから相手にあわせて、自分を変えているようなところもあるようだ。
カラオケで歌うのは「せつない恋の歌」。恋愛経験はまだないそうだが、気遣いの細やかな黄さんのこと、いつか、ありのままの自分を出せる相手と、幸せな恋をするのではないかと思う。
(取材・文:田中奈美 取材日:2016年9月14日)
![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

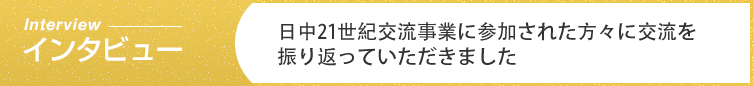











![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)