名前
段 暁霊(だん ぎょうれい) さん
プロフィール
中国湖北省武漢に1994年生まれる。心連心プログラム第五期生として2010年9月に来日。長崎日本大学高等学校に1年間在籍する。現在は早稲田大学商学部2年。日本のサブカルチャーが好き。お気に入りの漫画は「ダンガンロンパ」、「進撃の巨人」など。
経験を重ねながら
取材を行った日は、夏休みに故郷の武漢で過ごし日本に戻ってきたその翌日。武漢では、お母さんと2人でホラー映画を30本も見たと嬉しそうに教えてくれた。家で漫画や映画を見るのが好きで、どちらというとインドア派の段さん。日本に帰ってからも自宅に居ると、つい一日中映画やドラマを見続けてしまうと頭をかく。
「私はなかなか人目がないところでは勉強が進まない。他の人も勉強している図書館などへ行かないと、勉強できないんです」
アグレッシブに何事にも積極的に取り組むというよりは、自分のペースで少しずつ歩を進めるタイプ。しかしもちろんしっかり勉強しなくては、という気持ちは強く、大学でのサークル選びにもそんな意欲がうかがえた。
「サークルは『経済学会』というところに入りました。飲みサークルが大学には多いのですが、その中でがっつり勉強するサークルだと聞いて入りました」
またもうひとつ、英語を勉強するサークルにも所属している。将来、グローバルに働くには英語は必須と考えてのことだ。ただバイトとの掛け持ちが忙しくなり、次第に足は遠のいてゆく。2つ経験したバイトのひとつは居酒屋で、お酒の名前が覚えられなかったことから、もうひとつは終了時間が深夜近くになってしまうことからやめてしまった。今は「お金を稼ぐこと」がそれほど簡単なことではないことを痛感している。日本に来てまだ2年目。様々なバイトやサークルを経験することも大事だが、腰を据えてひとつのことに取り掛かる時期に差し掛かってきている。
 写真を拡大英語サークルの友人達とハロウィンパーティーに参加
写真を拡大英語サークルの友人達とハロウィンパーティーに参加
日本語を話すことが怖かった
心連心の第五期生として、長崎県諫早市に留学した段さん。思い出はホストファミリーの家に着いた初日にいきなり熱を出してしまったこと。それはこれから始まる生活への不安と緊張のせいからだったのだろうか。
小学校3年に転入した武漢外国語学校では、高校生に至るまで約7年間、日本語をみっちり勉強した。ただ、読み書き中心で会話の授業は少なかったため、来日当初は日本語を話すことが怖いと感じていたそうだ。
「当時は日本語を話して間違えてしまうことが怖かった。それに日本人のことも怖いと感じていたと思います」
おまけに留学先は長崎県。最初は九州弁になじめず、「休みの日になんばしたと(「何をしたの?」という意味)」などと聞かれて戸惑ったこともあるそう。また、武漢の街中で育った段さんにとっては、電車もバスも本数が少なく交通の便があまりよくない諫早市の環境が不便に思え、ホームシックになってしまった時期もあったそうだ。
「その時私は自転車にも乗れなかったのでとっても不便でした。正直心の中ではホストファミリーを変わりたいなと思ったこともあります」
しかしホストファミリーや先生、友人達の優しさに触れ、段々と今のこの環境を楽しもうと考えが変わっていった。
「自転車に乗れなかった私のために、ホストファミリーの同い年のかおるさんが、自転車の練習につきあってくれました。長崎は坂が多いからスピードがものすごく出て、すっごく楽しかった」
 写真を拡大長崎留学時代のホストファミリーと一緒に
写真を拡大長崎留学時代のホストファミリーと一緒に
また困った時には必ず助けてくれた教頭の梅本先生のことは、今でも思い出に強く残っている。
「なにか問題があったら、すぐ梅本先生を目で探していました。最後の送別会を、私ともう1人の留学生である馬さんを驚かせようとサプライズで開いてくれて、私と馬さんはもちろん泣いちゃいましたけど、梅本先生の目も赤くなっていたことを覚えています」
中国に戻ってからもう1度高校2年生をやり直すチャンスがあるかどうかを心配する段さんのために、中国の学校へ電話をかけてそのことを問い合わせてくれたのも梅本先生だ。段さんが大学生となり日本に戻った今も、先生が東京に暮らす娘に会いに上京した際には、一緒に食事をすることもあるそうだ。
実行委員を経験して
まだはっきりとした将来へ向けての目標が定まっていなかった段さんだが、同じ9月入学ということから仲良くなった韓国人の友人が、確固とした将来への夢を持っている姿には刺激を受けているようだ。
「彼女は韓国へ戻ったらサムソンで働きたいと言う夢を持っている。第二外国語で中国語を選択し勉強に励んでいて、目標があるのが素晴らしいと思います。私はとりあえず良い成績をキープしよう、と言う感じなので」
大学2年の時点で、将来への確固とした目標を持っている学生はどれくらいいるのだろうか。むしろ段さんの友人のようなタイプの方が少数派なのかもしれない。だからこそ羨望のまなざしを送ってしまうのだろう。
そんな段さんだが、今年ひとつの経験をした。心連心のOB達が企画した日中の大学生の交流を目的とする伊豆ツアーの実行委員を務めたことだ。日中の大学生30名が参加し、2泊3日で伊豆を視察し町おこしを考えるという企画だ。
 写真を拡大伊豆ツアーを企画した実行委員の仲間達と
写真を拡大伊豆ツアーを企画した実行委員の仲間達と
「三期生だった皇甫丹婷さんがリーダーを努め、私は渉外担当のリーダー。今までは与えられた仕事をするだけだったんですが、伊豆市役所と電話でやり取りしたり、皆に仕事を分配する立場になって、自分はこれまで甘やかされていたなぁと感じました。社会人ってこういうものなんだなと感じられた貴重な経験が出来たと思っています。バイトや期末試験が重なり忙しい時期だったけど、やってよかった」
ゆっくりとだが、着実に自信をつけていく段さんの姿が目に浮かんだ。はっきりとした目標ではないが、金融の中心でもあり香港で働きたいという夢を、今は持ち始めている。
違いもあるけど、共通点のほうが多い
来日当初怖いと思っていた日本人。実際に交流した経験も少なく、何を考えているのか分からなかったからなのだろう。でも今は、もちろん違いもあるが分かり合える共通点のほうが多いと感じている。
「尖閣諸島の問題があってから、東京=武漢間の直行便がなくなってしまいました。帰国するのが不便になってしまった私のことを周りの皆は不憫がってくれて。政治のせいで国民まで対立してしまうことなんて、誰も望んでいない。少なくとも私の周囲は日中友好を願っている人ばかりです」
日中友好を望んでいる若者は日本にもとても多い。そう日本や日本人に親近感を抱くようになったのは、やはり長崎の1年間があったから。当時のホストマザーとは、今でも季節の変わり目など折々に連絡を取り合っている。今年の段さんの誕生日には、手作りのケーキを宅急便で届けてくれたそうだ。日本のお米は高いと嘆く段さんのために、長崎産のお米とお菓子を詰め合わせて送ってくれたこともある。まるで上京した娘を地方から心配する本物の母親のようだ。
友人から、心配性だと言われると語った段さん。そんな彼女を離れがたい故郷である武漢やお母さんの元から自立への1歩へと背中を押したのは、長崎での1年間があったからこそなのだろう。今は日本語を話すことには不安はない。それは彼女が日本や日本人に寄せる信頼の証でもあるのだろう。
【取材を終えて】
「お母さんには娘ではなく息子のよう、と言われるんです」と意外なことを言う段さん。見た目はロングワンピースがお似合いのかわいらしい女の子そのものなのだが、「奥さんがほしいな。将来私が外で働いて、奥さんに家の中のこととか子守をしてもらいたい」と語るその見た目とのギャップに、思わず笑ってしまった。(取材・真崎直子)
![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

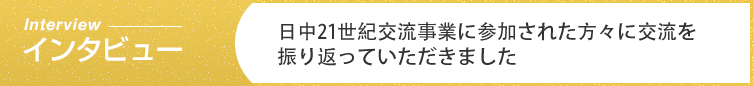
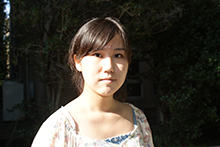












![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)