 写真を拡大続昕宇さんは普段はこのフォーラム事務室で執務している。
写真を拡大続昕宇さんは普段はこのフォーラム事務室で執務している。
名前
続 昕宇(しょく きん う) さん
プロフィール
1991年生まれ、山西省太原市出身。太原市外国語学校(高等学校に相当)で日本語を第一外国語として学ぶ。同校在学中の2007年9月から2008年7月まで「心連心」プログラム第二期生として栃木県の矢板中央高等学校に留学。
帰国後は山西師範大学の日本語学部に進学、さらに北京外国語大学大学院で日本文学を専攻した。16年7月に人民中国雑誌社に入社、「両京論壇弁公室(北京-東京フォーラム事務室)」に配属され、日中両国の交流活動の現場を中心に活躍中。
「家から近い」が始まりだった
 写真を拡大修学旅行で行った沖縄は大好きになった。景色の美しさや中国文化との近さに魅了され、その後は沖縄の文学にも興味を持つようになった
写真を拡大修学旅行で行った沖縄は大好きになった。景色の美しさや中国文化との近さに魅了され、その後は沖縄の文学にも興味を持つようになった
北京市内西部、政府機関や学校などが集中する地区に、多数の外国語書籍や定期刊行物を発行する中国外文局がある。外国人の姿も目立つ大きなビルの一角に、続さんの働く「北京-東京フォーラム事務室」はある。人民中国雑誌社は日本語雑誌『人民中国』を発行して60年以上の歴史を持つ老舗雑誌社だが、雑誌の出版だけでなく日中間の交流事業にも力を入れており、3年前からこのフォーラムの事務局を担当している。事務局の部屋は決して大きくはないが、日中両国の民間交流に重要な役割を果たす基地であり、彼女はそこで最年少のスタッフなのだ。
フォーラムの事務局で仕事をしていると聞くと、何やら堅苦しい人物を想像してしまうが、続さんはむしろ人当たりが柔らかく、とても人なつっこい印象。すぐに打ち解けて話を聞くことができた。まず高校進学に外国語学校を選んだ理由について質問すると、家から近い高校を選んだだけと屈託ない笑顔だ。数ある外国語の中から日本語を専攻したのも、「日本語にはたくさんの漢字が使われているので、学びやすいかなと思ったからです」と、軽い気持ちだったことを振り返る。もちろん、10年後に自分が日中交流の最前線に身を置くことになるなど、この時の彼女には知る由もない。
しかし高校3年間、1日に少なくとも2時間はある日本語の授業にしっかり取り組み、毎日出される宿題もこなしているうちに着実に力はついていった。1年後「心連心」に応募、第二期生として選抜され、2007年9月から栃木県にある私立矢板中央高等学校に留学することになった。
留学の思い出は部活と沖縄
 写真を拡大留学期間中は週末も吹奏楽部の部活に打ち込んだことが今も楽しい思い出として残っている。
写真を拡大留学期間中は週末も吹奏楽部の部活に打ち込んだことが今も楽しい思い出として残っている。
留学生活は順調で、中国でも優秀な成績を収めていた彼女にとって、古典を除いて日本の高校の授業はそれほど難しくはなかった。また、明るい性格の彼女はすぐに友達もできて、楽しい学校生活が送れたという。「毎日吹奏楽部の活動に通っていたことが、楽しい思い出です。楽器は日本に行くまで演奏したことがなかったのですが、パーカッションを担当させてもらいました」という彼女は、連日部活に打ち込んだそうで、「週末はほとんど吹奏楽部の練習や演奏会があったので、遊びに出歩いたりはしませんでした。演奏会のため他の市に出かけたり、今考えてみれば留学中は部活ばかりしていたような気もしますが、当時は本当に楽しくやっていました」という。
もう一つの思い出が修学旅行だと話す。「どこに行ったと思いますか? 当ててください」と話す様子に、それがとても楽しかったことがよく分かる。「実は、沖縄まで行ったんです。景色も美しく、文化も中国に近い部分があり親しみを感じました」とすっかり魅了された彼女は、これがきっかけで沖縄に強い関心を持つようになり、大学院の卒業論文では沖縄出身の又吉栄喜(またよし・えいき)の芥川賞受賞作『豚の報い』を取り上げたほどだ。現在も日本の小説は大好きだそうで、好きな作家は東野圭吾で、江國香織なども読むという。中国の小説にはスケールの大きな話が多いが、日本の小説には身近な物語が多く、そうした違いも面白いと感じている。
入社2カ月で東京出張
 写真を拡大2016年12月には日本のメディア関係者代表団の訪問交流に同行、貴州省を中心とした取材を、通訳を中心にサポートした。
写真を拡大2016年12月には日本のメディア関係者代表団の訪問交流に同行、貴州省を中心とした取材を、通訳を中心にサポートした。
実は彼女、かつては日本語教師になる希望も持っていた。しかし、日本語教師を募集する学校には博士課程修了を応募条件として求めるところが多く、彼女の希望にかなう仕事はなかなか見つからなかった。そこで進路の幅を少し広げて考えてみたところ、修士課程在籍中に聴衆として参加した「北京-東京フォーラム」を思い出し、運営を担当している人民中国雑誌社に応募し、見事採用されたというわけだ。
「国際的な交流活動に興味があったので応募しましたが、入社するまでフォーラムの事務局がどのような仕事をする職場なのか、全くイメージが湧きませんでした」という彼女だが、2016年7月に入社するとすぐにフォーラム事務局に配属され、2カ月後の9月にはフォーラム開催地である東京への出張を命じられた。留学時代以来の日本だったが、久しぶりの訪問は仕事に追われホテルとフォーラム会場を往復するだけで終わってしまった。「9年ぶりだったのですが、仕事が忙しく日本を感じる時間はありませんでした」。
2016年には、福田康夫元首相が基調講演を行った。日本側主催者は言論NPO、中国側の主催者は中国国際出版集団(中国外文局)で、中国側の運営を同局傘下の人民中国雑誌社が受け持っている。
新人の彼女にとって、こうした重要な場に参加し、仕事で日本語を使って運営に関わる経験はどんなものだったのだろう。「新入社員としては、分からないことが99%。ただ指示通りに動くだけでしたね」と謙遜するが、事前にはメールやパンフレット、アンケートの設問などの翻訳、会議資料の準備など多数の仕事をこなし、とにかく忙しかった。そして、日本に到着してからは、いくつかある分科会のうち、特別分科会の事務局業務も任された。「写真を撮影したり、録音したり、パネリストのみなさんの案内、誘導もしました。ボランティア・スタッフの作業手配などもありました。さらに、帰国してからは分科会についての記事も書きました。その時は大変でしたが、今振り返ってみて、特に何かを達成したというような実感はありません」という感想は、彼女の成長の証だろう。「いずれにしても貴重な体験でした。ずっと学校で学んできて、初めて社会に出ましたが、そこですぐに国際的な会議に参加させてもらって視野がぱっと広がった感じです。今後は頑張って、もっと全体を理解できるようになりたいです」。
青年団や記者団に同行
 写真を拡大2016年12月、日本のメディア関係者代表団の訪問交流に同行。北京の中関村で起業をサポートする組織を訪問した際には、起業関係、IT関係の専門用語を駆使して通訳した。
写真を拡大2016年12月、日本のメディア関係者代表団の訪問交流に同行。北京の中関村で起業をサポートする組織を訪問した際には、起業関係、IT関係の専門用語を駆使して通訳した。
フォーラムが終わると、ひと息入れる間もなく10月末から11月にかけて人民中国雑誌社が行っている「Panda杯全日本青年作文コンクール2016」の受賞者たちによる北京、揚州、上海訪問に同行し通訳を担当した。「内容も難しく緊張するフォーラムとは違って、若者ばかりでリラックスした雰囲気でしたし、皆話しやすく、同行していて“超”楽しかったです。そして、私自身がこういう交流イベントに特に興味があることを再認識しました」。
さらに、12月には国務院新聞弁公室が招いた日本のメディア関係者代表団の訪問交流に通訳・案内役として参加した。中国外文局がこの訪問交流の運営を担当、続さんたちに現場の仕事が回ってきたのだ。彼女は貴州省を訪問するグループに付き添い、通訳を中心に日本の記者たちの取材や現地の人々との交流をサポートした。「フォーラムや青年交流とは異なった楽しさがありました。70年代、80年代生まれの比較的若い記者さんたちばかりで年齢も近く、さらに同業ですので話題もいろいろあり、友達もできました」。しかし楽しいといっても仕事である以上当然、苦労もあった。「グリーン成長というテーマでの取材でしたが、通訳のためには関連用語も調べておく必要があります。北京の中関村で起業について取材する予定があったため1週間ほどかけて起業や技術関係の言葉を集中的に事前勉強しましたが、それでもとても難しかったですね」。
日本と関わり続けたい
 写真を拡大大学院生の時に北京で開催された第9回のフォーラムに聴衆として参加した時の写真。この時はまだ、東京で行われる第12回に自分が事務局スタッフとして関わることになるとは思っていなかった
写真を拡大大学院生の時に北京で開催された第9回のフォーラムに聴衆として参加した時の写真。この時はまだ、東京で行われる第12回に自分が事務局スタッフとして関わることになるとは思っていなかった
このように、7月に入社したばかりの新人としては、内容的にも量的にもかなり充実した仕事ぶりで、第一線でバリバリ活躍している印象だが、彼女は全く浮ついておらず、自分の立ち位置をきちんと理解している。「今後はフォーラムやイベント運営と同時に、雑誌についても勉強していきたいですね。これまでに記事は2本書きましたが、まだ雑誌づくりのことは何も分かりません。雑誌社で働く者として、雑誌づくりの基本をきちんと理解し、記事の書き方や翻訳力もつけていく必要があると思っています」。
最後に彼女は「一歩一歩前に進むことができればいいかな。日本と関わりのある仕事をずっと続けていきたいです」と、シンプルな言葉で自分が見据える未来を語ってくれた。
【取材を終えて】
日中関係に複雑な局面が続く中、民間交流の重要性が高まっている。これからの交流には言葉の通訳ができるだけでなく、自分の経験によって深めた相手国への理解をベースに交流ができる若い人材の活躍が必要だが、彼女はまさにそうした人材の代表格だ。能力の高さやユニークな経験だけでなく、彼女には自然体で人好きのするキャラクターがあり、インタビューをしていても、強く自己主張するわけでもないのに前向きな姿勢が伝わってくる。留学でできた絆は今でも大切にしているというが、そうした人間性がこれからの彼女の活躍を保証しているように思う。
(取材・文:井上俊彦)(取材日2017年1月20日)
北京-東京フォーラム
http://tokyo-beijingforum.net/
![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

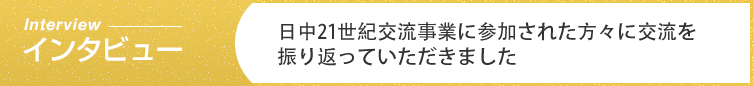












![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)